いつもお世話になり、ありがとうございます。事務局の青柳でございます。
「学びのコーナー」にて、有城 蘭カウンセラー(北海道)の記事を更新いたしました。
今回更新の、自分で心の痛みを癒す方法のレポートでは、自分でできる心の痛みの応急処置の方法について、有城 蘭カウンセラーがご紹介しています。
皆様のご参考になれば幸いです。
投稿者プロフィール
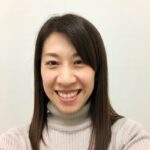
最新の投稿
 あおやぎ(浜松)のつぶやき2026年1月4日学びのちからについて
あおやぎ(浜松)のつぶやき2026年1月4日学びのちからについて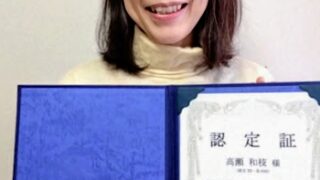 あおやぎ(浜松)のつぶやき2025年12月23日卒業生のお言葉を頂戴しました(高瀬 和枝さん 群馬県吾妻郡)
あおやぎ(浜松)のつぶやき2025年12月23日卒業生のお言葉を頂戴しました(高瀬 和枝さん 群馬県吾妻郡) あおやぎ(浜松)のつぶやき2025年12月2日学びのコーナー(掛川 恵二カウンセラー)更新しました
あおやぎ(浜松)のつぶやき2025年12月2日学びのコーナー(掛川 恵二カウンセラー)更新しました あおやぎ(浜松)のつぶやき2025年11月1日プロカウンセラーの声(有城 蘭カウンセラー)更新しました
あおやぎ(浜松)のつぶやき2025年11月1日プロカウンセラーの声(有城 蘭カウンセラー)更新しました




