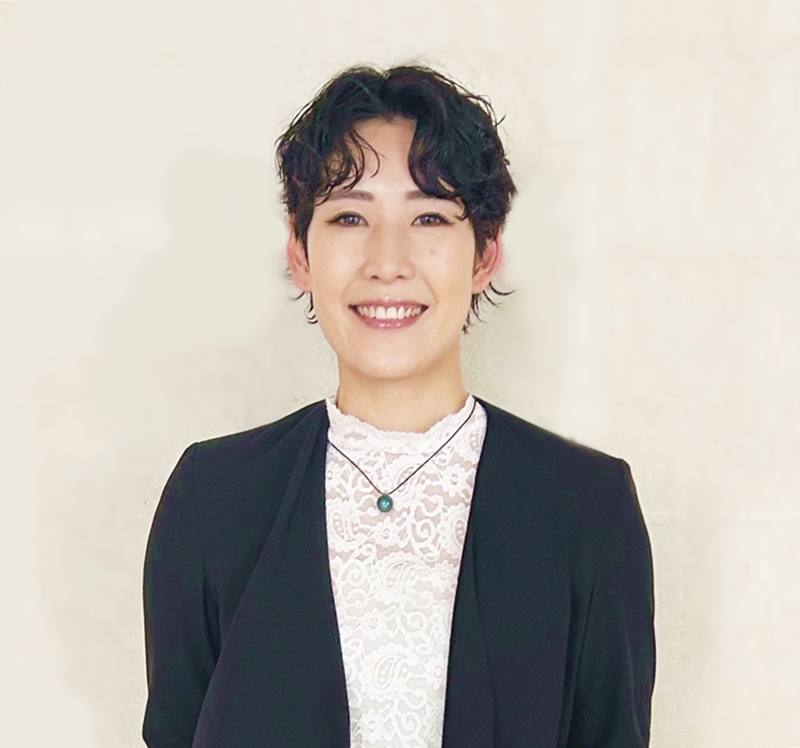親子の関わり方 〜マルトリについて〜
くれたけ心理相談室 松戸支部の鈴木 千尋です。
<はじめに>
みなさん、マルトリという言葉をご存知でしょうか。
このテーマを取り扱うきっかけとしては、前回のレポート(機能不全家庭について)にも記したように、自身の親との関わりをたくさん見つめてきたことが大きかったと思います。
そして今、自分と子供の関わり方について改めて考える機会が多いです。
子育てはリアルタイムで正解がないものばかりで不安も多いです。常に自信たっぷりな母ではないけど、子どもの頃の経験と親としての立場、どちらからの目線も持って初めて理解ができた部分があると実感しています。
そんな中である本を読んだときに“マルトリ“という言葉を初めて知り、興味を持ち独自に学びを深めたことから、この機会に整理し、アウトプットさせていただきたく取り組ませていただきました。
マルトリとは
正式名称 マルトリートメント(Maltreatment)
どの家庭でも起こり得る「大人の子どもへの避けたい関わり」を意味しています。
Treatment(扱い)にmal(悪い)が繋がった言葉で、不適切な養育と訳すことができます。
具体的には声を荒げて怒鳴る、他の子や兄弟と比べる、子どもの前で親同士の言い合いを見せるetc…
これらは虐待とほとんど同義ですが、子どもの心と身体の健全な成長・発達を阻む養育全般を指す、より広い概念とされています。
WHO(世界保健機関)のチャイルド・マルトリートメントの定義では、18歳未満の子どもに対するあらゆる身体的・心理的・性的虐待とネグレクトを含み、子どもの心身の健康、発達、対人関係などに害をもたらすこととされています。
また、マルトリは親や祖父母など直接的な養育者のみに使われるものではなく、保育や学校など子どもと関わるすべての大人からの避けたい関わりを指しています。
マルトリの影響
マルトリを受けた子どもは私たちの想像以上に心に大きな傷を負っています。そしてもう一つ、心と同じように大きな影響を受ける部分があります。それは脳です。
アメリカ・ハーバード大学医学部精神科学教室の研究で、厳しい体罰などの不適切な養育が脳にどのような影響を与えるかを研究したところ、子どもの頃に受けた過度なストレスが脳の構造を変形させることを発見。
身体的マルトリによって脳の前頭前野が縮むという研究結果もあります。
前頭前野が萎縮すると、犯罪抑制力の低下や素行障害、うつ病のリスクを高め、攻撃性があらわれることもあります。
さらに体罰や暴言、性的虐待、ネグレクトなど、虐待の種類によって脳の中でダメージを受ける部位が異なることも明らかとなっているようです。
日常で起きやすいマルトリ
①身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
殴る、蹴る、叩く、突き飛ばす、首を絞める、火傷を負わせたり、溺れさせたり、縄で拘束するなど。
②性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること。
子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る、ポルノグラフィティの被写体にするなど。
③心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。拒絶的な態度や同居する家族に対する暴力などもこれに当てはまります。
言葉による脅し、無視、兄弟間での差別、子どもの前で暴力を振るうなど。
④ネグレクト
保護者としての監護を著しく怠ること。児童の心身の発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置。
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かないなど。
傷ついた脳を癒し回復させること
上記で記したようなマルトリ行為を長期間受け続けると脳にも心にも影響が出るというのは簡単に想像ができるかと思います。しかし、1度傷ついた脳は回復できないわけではありません。それには適切な治療とケアによって回復できるということが近年の研究でわかってきているそうです。
どの治療やケアにも第一に必要なのは子供にとっての安心と安全です。
不安定な環境にいる子にがむしゃらにケアをすることよりも、まずは子供が安全かつ安心して生活を送れる環境(必要があれば児童養護施設など)を整える必要があります。
その上で薬物療法、心理療法、遊戯療法などを取り入れることが望ましいとされています。
トラウマ克服に効果的とされているEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)もマルトリによって心に傷を負った子供に有効とされますが、年齢の低い子供は言語化することが難しいため明らかな効果は立証されていません。
そんな年齢の低い子供には「バタフライハグ」という技法が効果的です。
手をクロスし、過去のマルトリの経験に意識を向けながら、左右の肩を交互にリズミカルにたたきます。終わった後に生じた自分の気持ちなどを話しながらこの動作を繰り返していくうちに、心を落ち着かせることができ、過去の経験をより穏やかな気持ちで振り返ることができます。
ペアレントトレーニング
マルトリをしてしまう親の脳も傷ついてきた可能性が高いということが想像ができます。
マルトリを受けた子のケアと、親の育児ストレスの緩和も一緒に癒していくことが好ましいと感じます。
ペアトレは1960年代からアメリカを中心に発展してきたトレーニングです。
当初は発達障害の子を持つ親に向けた子育てトレーニング法とされていましたが、現在は子育てに不安がある親をサポートするものとして広く使われているものです。
マルトリ予防
マルトリによって傷ついてしまった心と脳を癒すことは重要ですが、マルトリを予防することも同じだけ重要であると感じています。
家庭という小さな世界で起こっていることで見えにくいこともありますが、必ずサインがあります。そのサインをいち早く見つけることができれば必要な支援機関に繋ぐなどしてマルトリを防ぐことができるかもしれません。
一つは歯科検診によって発見しやすいとされています。
ネグレクトのように好ましくない家庭環境で乱れた生活によって虫歯になりやすかったり、栄養の偏りによっての歯の成長も変わることから、口腔内の状態を見て適切な治療がなされず放置されている様子が分かれば学校や児童相談所と連携し必要な支援に繋ぐことができます。
社会にできること、支援について
マルトリについて学んでいく中で感じたことは、その親自身がマルトリを受けてきた人の他にも、褒められたり自己を肯定されてこなかった方が苦しんでいる延長にある状況ではないかと感じました。
子供を必要以上に強く叱ってしまうことも、手を挙げてしまうことも、されてきたことしか方法がわからなかったり、されてこなかったことは全く見当がつかない。そういった状況にあるのではと想像してみること、考えてみることから理解が深まると感じています。社会全体にマルトリが認知されるために、マルトリについて考える。自分から、身近なところから始まる小さな考えが繋がって広がっていけるといいですね。
子どものケアと親の支援、どちらも私たちカウンセラーは関わる可能性が十分にあります。子育てに対する不安感や、子供に対しての接し方、又は親自身がマルトリを受けたと自覚がなくても大人になった今生きづらさや苦しさを感じていることなど、普段いただくご相談内容として取り扱ってきたご経験があるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
1人で抱え込んできたクライエント様が多いと感じます。
1人でなんとかしてきた人、1人でやらざるを得なかった人、頼り方がわからず苦しんでおられると思います。
カウンセラーとして、支援を必要とする人たちの手にきちんと届くよう、支援の入り口としてカウンセリングの場が活用されることが大いにあるという認識を持ち、勇気を出して手を伸ばしたクライエント様の手をしっかり握れるよう、知識や理解はもちろん、具体的な予防法や対処法、必要な支援所との連携に関することと、多岐に渡る部分に目を向けていくことの大事を再確認いたしました。
まとめ
マルトリはどのご家庭でも起こりうることとして決して他人事にせず捉えていくことが必要だと思います。
そして、マルトリは子育て困難家庭のSOSでもあります。
気軽に相談や支援が受けられる場所があることを知ってもらえるよう発信していくことが私にできることの一つであると考えました。
子育てが「孤育て」にならぬように。
繋がりを作る、情報を得るという部分でのサポートを行なっていきたいです。
拙い文章となってしまいましたが、ここまでご覧くださりありがとうございました。
参考文献:「最新脳研究でわかった子どもの脳を傷つける親がやっていること」
著者 友田明美(小児精神科医)
くれたけ心理相談室 松戸支部 鈴木 千尋
鈴木 千尋 公式サイト